およそ10年ぶりに岬 龍一郎氏の「欲しがらない生き方」を読み返しました。
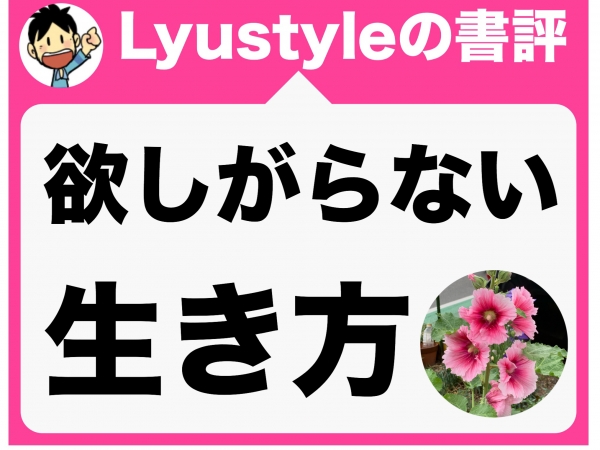
著者の岬氏は、バリバリのサラリーマンで、社長にまで上り詰めた人でしたが、ガンによる闘病生活の中で、これまでの人生を振り返ります。
仕事ばかりで何の楽しみも持たなかった自分がそこにいました。
そこで社長や役員などの肩書きを脱ぎ、その後の人生を、半隠遁生活によるほどほどの仕事で楽しみに生きる生活を目指します。
それは決して我が儘勝手な生き方ではありません。
仕事はきちんとして社会的責任は果たすのです。
でも、ことさらに栄達を求めたり、上司のための仕事をしたりなどで自分を追い詰めず、ほどほどにして人生を楽しむ余力を残しておくという生き方です。
そのことを漱石の作品に度々出てくる「高等遊民」になぞらえ、現代版の高等遊民になることを提言します。
高等遊民とは、親の財産のもと、相当高い知的教養がありながらも当時の世の体制に合わせることを拒み、悠々とした知的生活を行なっていた人々のことです。
私はこの本を読み進めながら、多様な古典の記述と向かい合うことになりました。
セネカ、吉田兼好(徒然草)、ソロー、ホイジンガ、白居易、良寛、歌人橘曙覧。あの、「楽しみは・・・」の歌人ですね。国語の教科書に載っています。
これらの方々の著作や生き方に出てくるキーワードが、「ほどほどにやって余裕を持たなければ人生は楽しくないよ」ということなのです。
橘曙覧などは、幕末の賢公松平春嶽からの再三の士官の求めにもかかわらず、自分の咲くところはそこではなく、誰からも知られずにただ歌を作ってほどほどに過ごすことだという歌を返しています。
まさに悠々たる知的生活。
私が若い頃から目指してきた生き方です。
そのために、私が教師であったことは幸せでした。
教師にとっては、栄達への欲望はほとんどないからです。
日々子供たちが目を輝かせる授業を「生産」し、実際に子供たちの「うわー」と喜ぶ声を味わい、子どもたちが帰った後の教室で今日のことを振り返る。
そしてまた、明日の準備をする。その繰り返しです。
そこには、自分が出世したいというような考えや気持ちはほとんど入ってきません。
むしろ、「出世」すると、子どもたちと共にある生活を捨て去らなければならないからです。
できれば、いつまでも教室で子どもたちと共にありたい。
それでも、誰かがやらなければならないから、声をかけられたら潔くその道に進まざるを得ないですね、という気持ちでまあ日を生きています。
ですから、教師は時間に追われてブラック極まりない職業ですが、当の私は栄達などに心奪われることなく、私の中の満足できるほどほどのところを、自分で設定して生きてくることができました。
それが、「可処分時間2時間」の生き方です。
なるべく寝るが寝るまで授業のことばかり考えまい、可処分時間をちゃんと意識し、本を読み、家族と談話をし、絵を描き、ぶんをつくる生活も大事にしよう、それが私のほどほど。
そうしないと、本当に一日中、授業や教室のことばかりやってしまうのです。
幅が広がりません。
落とし穴は栄達への欲求ではなく、「授業巧者」として名を馳せたいというところにあります。
職人として上達した教師という姿への欲求です。
栄達への欲求はなくても、職人としての上段者になりたいという欲求からの無理にはよく陥りがちです。
教師には職人としての側面がありますから当然ですけどね。
でも、そらもほどほどにしなければね。
私はその道を求めすぎるあまり健康どころか心までも損ねてしまった人を何人も知っていますから。
自分語りになってしまいましたね。
ほどほどの現代版高等遊民の生活。
定年後の準備としても大切なことです。
退職してからまで現職中の自分がどんな地位にあったかを自慢する人の話ほど面白くないものはありません。
もしかしたら、40代後半を迎えていた10年前の私は、この本を病読んで定年後の助走を、意識し始めたのかもしれません。
こちらの記事もどうぞ
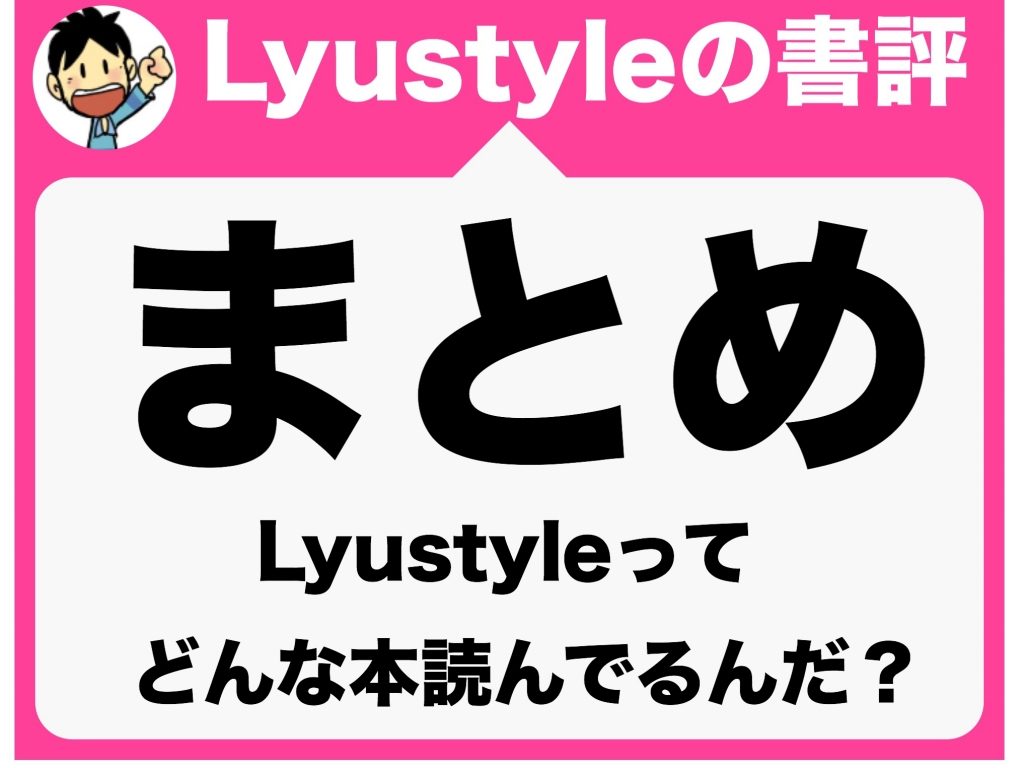
私のメルマガで配信している書評を記事にしてまとめています
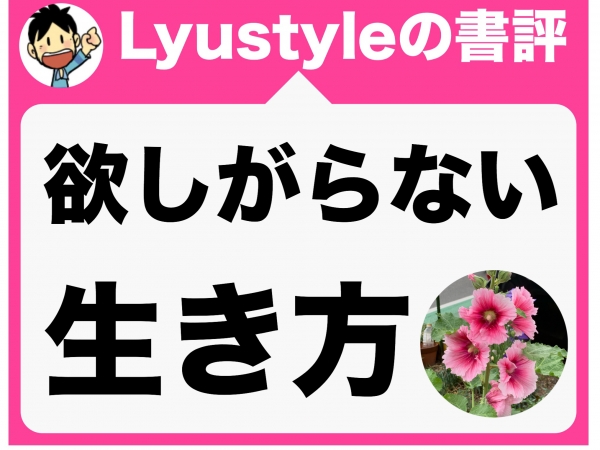
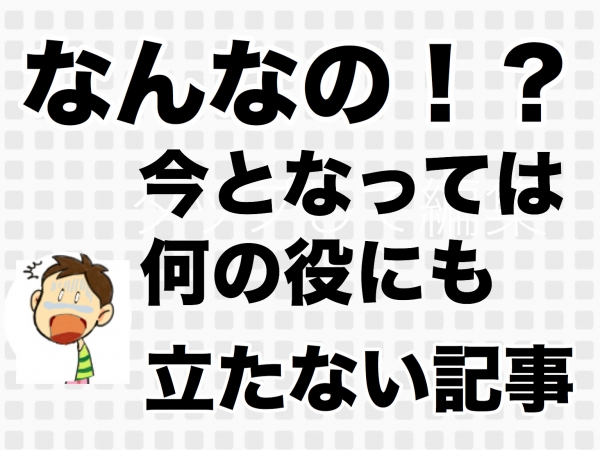

コメント
自分語りの部分がとても面白かったです笑
なるほど確かに教師は昇進欲求が少なく、職人としての上達欲求が高い職業ですね。
ありがとうございます。
管理職になって何かいいことがあるのかというと大変なことばかりのような気がします。
しかし,お呼びがかかれば私の力でよければ・・という気持ちでこれまでやってきました。
いちばんしあわせなのは,授業しているときですね。
[…] 🍏欲しがらない生き方 […]