タイトルを見ると,意味不明でしょ?
保存できない?
じゃ,なんで使うの?
ということになるわけです。
1984年頃までのワープロにはフロッピーディスクドライブがついてなかったんです。
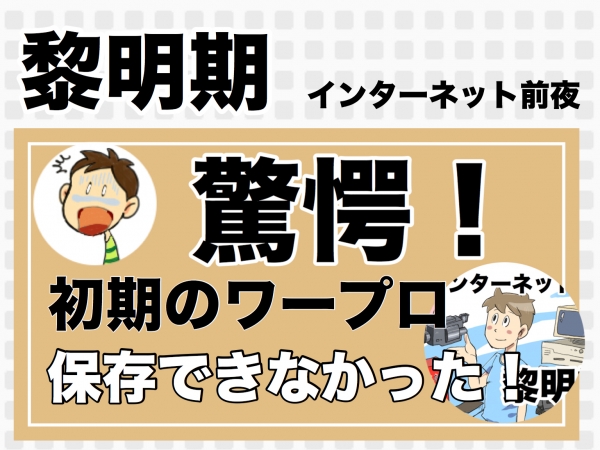
「ワープロ買ったけん,家にきてみやい」
なんだか,おそろしい誘われ方ですが,いわゆる博多弁でいうとこうなります。
一般的には,
「ワープロ買ったよ。だから家にいらっしゃい」
となります。
それはおいといて,1984年の私は,当時の40代の教務主任の先生から誘われました。
「ワープロって,あれですか。タイプライターみたいなやつですか」
「そうたい。はよ来やい!( 訳: そうだよ。はやくおいで)」
決して喧嘩しているわけではありません。
ワープロは,当時,テレビのCMでもあまり見たことない代物。
ワープロブームで大爆発するほんの3年ほど前の話です。
先生のうちで,時代の最先端のワープロを触らせてもらいました。
人差し指で,そのへんの文書の文字をひとつひとつ売って,単語ごとに変換キーを打って変換しました。
「僕は」を打つのに,
「ぼく」 変換キー →「僕」
「は」 確定キー → 「は」
のような単漢字変換で,まだ「僕は」という文節変換はなかったと記憶しています。
一行書くのに10分くらいかかったでしょうか。
大きなディスプレイがついたCRT型はまだ90万くらいしていた時代。
先輩が買ったのは 後年のポータブルワープロ型で,ディスプレイは1行か2行ほど。
それでも,自分が打った文章が活字として電子的にディスプレイに表示されているというのは,すごい体験でした。
未来を感じました。
人類すごい!
そう思いました。
次に思ったのは・・・
「で,これ,どうするの?」
ということでした。
先輩はとくとくとして「印刷」というキーを押しました。
すると,ぎーという音がして,なんと,後ろからその文字が印刷されてでてくるんです。
まだ,たてよこ16ドットというとんでもない低解像度の文字でした。印刷用に使えるようになったのは,24ドットになってからで,16ドットなどはつかいものになりません。
しかし・・・
未来をかんじました。
鉛筆やボールペンを使わずに,紙に文字を生み出せるのです。
こんな経験は,タイプライターの国ではまあ経験済みでしょうが,それにしてもスタンプでポンポン文字を打つのですから,直接的に文字を書いている気にはなります。
ワープロは,書くことと,印刷することとが完全に分かれています。
時間の差を生じさせることができるのです。
タイプライターだとこうはいきません。
今打って,今印刷です。
ワープロは,家で打っておいて,職場で文字として印刷できる,すなわち「タイムシフト」ができるのです。
まさか,当時はそこまで考えませんでしたが,ただ,今 目にしている機械が,人類の知的生産のあり方を変えてしまうほどのポテンシャルを持ったとんでもないものだ,なんて思いもせず,すなおに「すごい!すごい!」と喜んでいました。
私が24歳の時のこと。
そのうち,先輩が職場にワープロを持ってきました。
「先生!それ貸してください!」
私は,当時サークルの広報を任されたときだったので,原稿をそれで打たせてもらおうと思ったのでした。
「おう!よかばい!つかってみんしゃい!( 訳:おう!いいよ!つかってごらん!)」
私は喜び勇んでキーを打ち始めました。
まだブラインドタッチなんて知りません。
一文字一文字大事にキーを押して行って,単語ごとに漢字を確定。
2時間くらいかけてA4一枚程度の文書をつくりあげました。
効率なんてまったく考えていませんでした。
ただ,おもしろかったのです。
「できました!さあ!印刷するぞ!」
その時,別の先輩が私の後ろをすっと通ります。
おわかりですよね?この後に起こった悲劇。
そうです。
その先輩の足は,見事にワープロにつながっているコードをひっかけました。
コンセントはぬけ,ワープロは一瞬にして電源が落ちました。
「あれ!!」
急いでコンセントを入れ電源を入れましたが・・・・・
2時間の仕事はすべて水の泡となってしまいました。
そう,当時の文書は,保存しておくことができなかったのです。
打って電源を落とすまでの一回切だったのです。
保存しておいて後で呼び出して更新するという,人類の知的生産のありかたを一変させるあの大革命がおこるのはその1年後。
しかし,わたしは,その経験で,見事にワープロを「ただの文書清書機!!」と決めつけ,後年の「職場での購入,大反対!」側にまわることになります。
そして,この記事へとつながります。
1980年代に初めてワープロに出会った人たちは何を感じていたのか
こちらもどうぞ
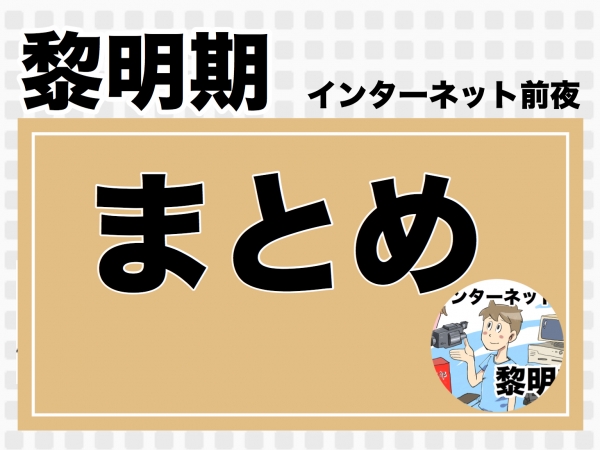
更新履歴
2019-7-6 公開
2021-3-25 修正と追記
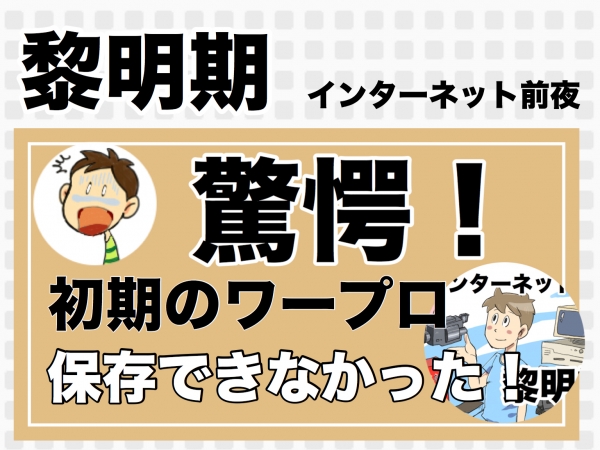
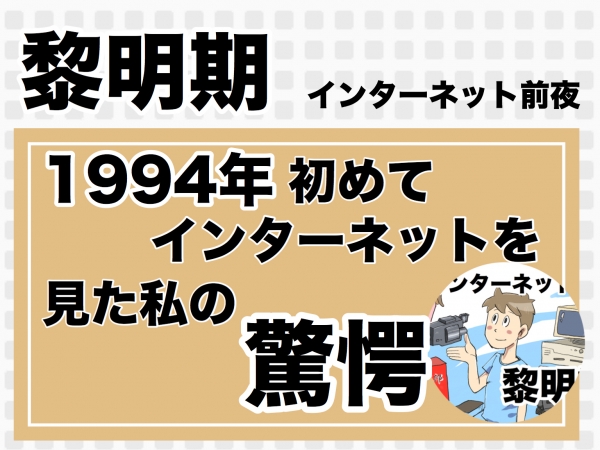
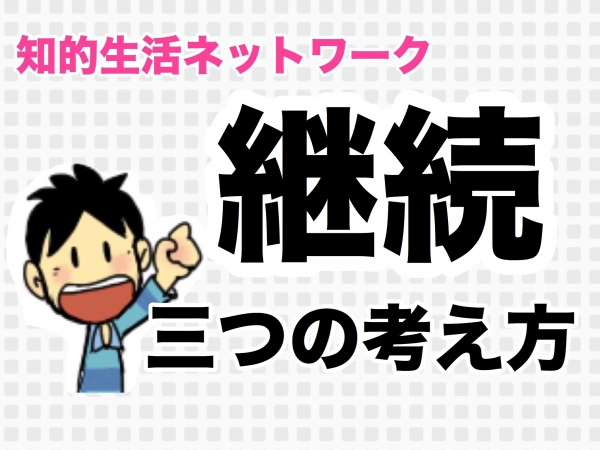
コメント
[…] 驚愕!初期のワープロは保存できなかった […]
[…] 驚愕!初期のワープロは保存できなかった […]