「遅読」についてどこかで記事にしたなあと思ってさぐってみたら,こちらにありました。
【読書】わたしの読書についての覚書2015版 | 知的生活ネットワーク
私自身はことさら遅読を実践しているわけでありませんし,「遅読」を特にすすめるわけでもありません。
速読も遅読もそれぞれの目的によってどちらも必要としています。
読書のひとつの方法です。
しかし,速読の本は世にたくさん出ているのに,「遅読」に関する本はあまりありません。
何事もバランス感覚が必要であると思うのであらためてこの本「遅読のすすめ」をクローズアップしてみたくなりました。
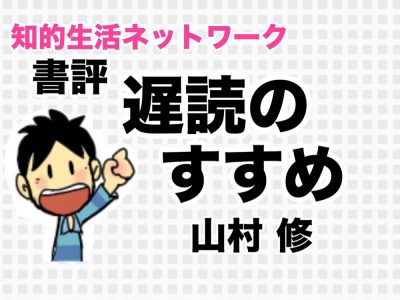
著者の山村修氏は,大学の図書館司書を務めながら,日刊ゲンダイの書評を長きにわたって続けた書評家です。
ご自身の読書スピードは1週間に1冊,月に4,5冊ほどであり,遅読を大事にされました。
速読がもてはやされる風潮の中で,2002年にこの本を著しています。
目次
遅読と心身のリズム
ここに次のような文章があります。
「目が文字を追っていくと,それに伴いながら,その情景が表れてくる。
目の働き,理解の働きがそろっている。
そのときはおそらく,呼吸も,心拍も,うまくはたらきあっている。
それが読むということだ。
読むリズムが快く刻まれているときそれは読み手の心身のリズムと幸福に呼応しあっている。
読書とは,本と心身とのアンサンブルなのだ」37
本を読んでいると何だか知らないが焦っているときがあります。
呼吸が乱れ,心臓がどきどきすることがあるのです。
なぜかはわかりません。
読んだ本の内容に高揚しているのでしょうか。
それとも,短い時間の中で今日中にまだこれだけ読まなければならないと思ってのことなのでしょうか。
いったん立ち止まって考えたいが,先に進みたくもある。いったいどうしたらいいのか,という混乱でしょうか。
おそらくそのどれもがあてはまるのでしょう。
そしてそのような状態に陥った時点から,私の読書は空虚なものになっていきます。
頭に入らないのか,飽和するのか,とにかく読んだものがくっきりとした形となって頭にはいってこなくなるのです。
そういう時には,本をいったん置くことにしています。
そういう状態のことが,この一文によく説明してあると思いました。
そういう状態ではない時,つまり快適に読書をしているとき,私の目の働き,理解の働きがきっとそろっているのだ。呼吸も心拍もうまくはたらきあっているのでしょう。
遅読と速読の切り替え
遅読がいいのだ,とか速読がいいのだ,いうことを思っているわけではありません。
速読により,さっさと必要な情報だけ抜き取っていく読み方で十分な本もあります。
そういう本は,そういう読み方をしているときに,きっと目の働きや理解の働きがそろっているのです。
呼吸も心拍もうまく働きあっているのに違いありません。
ゆっくり読もうと思いながら小説を読んでいるとき,または,さっさと必要な情報を得ようと速読により情報本を読んでいるとき,
もし焦燥感が表れ,頭に内容が入らなくなり,心臓がどきどきし,呼吸が乱れて来たら,その読み方をやめたらいいのです。
きっとその読み方のリズムが自分の心身のリズムに合っていないのです。
一冊の本を遅読と速読で読み,必要なタイミングで切り替えましょう。
山村氏は3回目の遅読「吾輩は猫である」で,これまで読み飛ばしてきたある一行を発見したと言います。
スイスイ読み飛ばしていくような読み方で,その一行にまで落とさずに目が行き,読み味わえる状態なら,それはそれで心身のリズムにあっているのです。
速読すればいいのです。
普通なら1ページ1秒ほどで速読できる自己啓発本を読んでいるとき,急に頭に入ってこなくなったら,じっくりと腰を据えて遅読すればいいのです。
きっとそこには,知識の新たな地平が広がっているのかもしれません。
遅読と多読の折り合い
遅読は一つ一つの言葉を吟味しながらゆっくりと,行きつ戻りつしながら読み味わうことです。
多読は,たくさんの本に出合うことです。
この二つは一見相反しているようですが,実は対立概念ではありません。
遅読しながら多読することは可能なのです。
例えばこのブログでは20冊並行読書という読み方をお勧めしています。
この読み方は,1冊1冊にとっては相当な遅読です。
しかし,「読みとおす」ということを前提にしていないので,たくさんの本に出合うことができます。
一生のうちに何度も読み返す「至高の一冊」に巡り合うために行う並行読書。
多読でありながら,遅読です。
じっくりと数ページの本を読みならも,たくさんの本に出会えます。
多読の方法は,速読ばかりではないということですね。
更新履歴
公開:2016-3-12
追記:2019-5-19
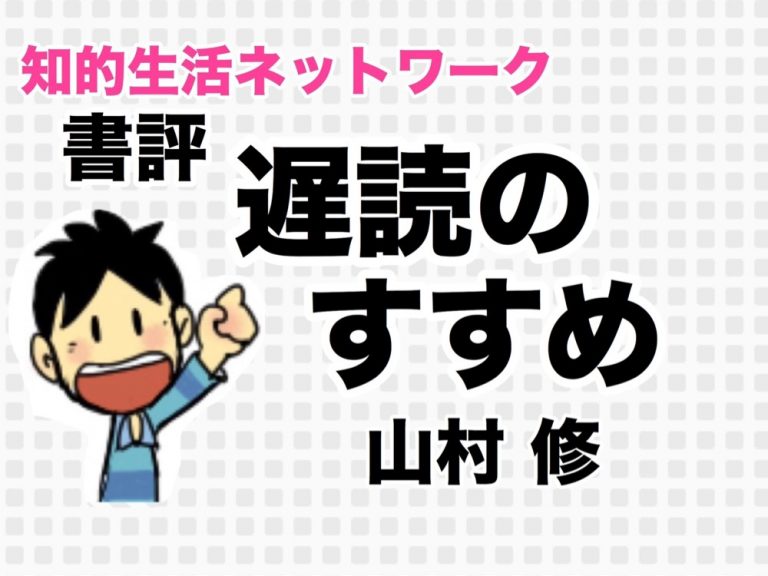


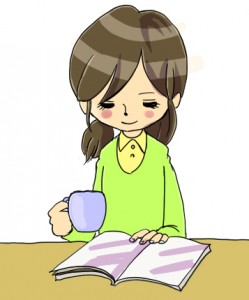

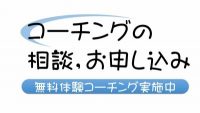
コメント
[…] 🍏「遅読のすすめ」 山村修 […]