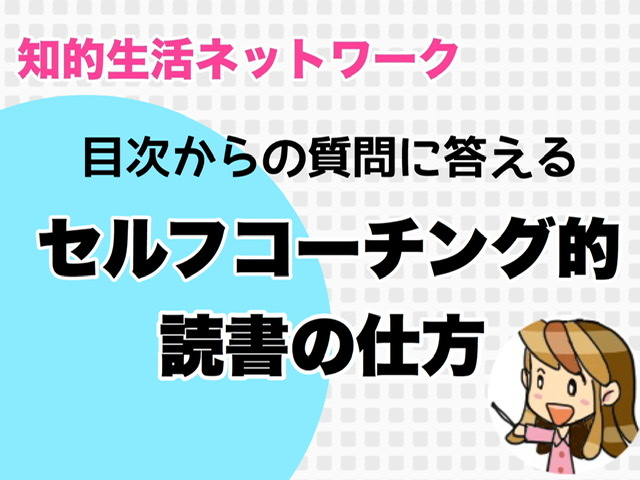
ちょっと前、こんなツイートをしました。
本をざっと読んだ後、目次を読みながら「何が書いてあった?」と自分に問います。
答えられないところ、面白くてもう一回読みたいところを再度読みます。
目次をみて、もういいかなと思う本は、今の自分に縁がなかったと、一度書庫で眠ってもらいます。
後から大復活を遂げる
ステップにするとこうですね。
- [st-timeline myclass=”” add_style=””]
[st-timeline-list text=”step.1″ myclass=”” fontsize=”” fontweight=”bold” color=”#9E9E9E” bgcolor=”” center=””]目次をじっくり読んで,本をざっと読み全体を把握する
[/st-timeline-list]
[st-timeline-list text=”step.2″ myclass=”” fontsize=”” fontweight=”bold” color=”#9E9E9E” bgcolor=”” center=””]目次に戻り,目次を質問とみなして「何が書いてあった!」と自分に問う。
[/st-timeline-list]
[st-timeline-list text=”step.3″ myclass=”” fontsize=”” fontweight=”bold” color=”#9E9E9E” bgcolor=”” center=””]答えられなければ,その部分を読み返す[/st-timeline-list]
[/st-timeline]
これが、結構見られてて、バズったと言うほどではないけど、何人もの方から「いいね!」をいただきました。
どうも、「目次に戻る」と言うところが、皆さんに響いたようです。
目次をしっかり読んでから全文をざっと読み、全体を把握する、と言う読み方は、実用書とかフィクションなどの読書でよく用いられます。
僕も、よくやります。
初めから「虫の目」で読んでると、この文が全体のどんな役割を持っているのか、どんな板にあるのかがわかりにくく、結果として線やハイライトの意味が後からわかりにくくなるのです。
全文をざっと読んで全体像を頭に入れてから読むと、ハイライトの入れ方も変わるんですよね。
で、僕の場合は、そこからもう一度目次に戻ります。
目次を質問者にして、自分に問いかけてもらうんですね。
目次のその文言を質問に見立ててそれに答えられるか。
それを実際に言葉に出しながら答えていくんです。
考えるんじゃなくて、実際に言葉に出すんですよ。
言葉が、わかったことを引き出してくれます。
言葉にしないと「わかったつもり」のままになるんです。
言葉にできたことだけが「わかったこと」なんです。
ところが、目次からの質問に答えられないことがあります。
モゴモゴしたり、ごまかした言葉になったり、いつもの口癖の言葉に置き換えたり。
つまり、わかってない。
それで、そこを再読するんです。
このやり方がいいなをくださった皆さん、新鮮だったようです。
このような言葉もいただきました。
ここまで反応していただいてすごく嬉しかったと同時に、それをやっているのは私がコーチだからかな?と思いました。
コーチって、相手の潜在的な思いを、質問によって引き出して顕在化させ、その気づきを行動に結びつけるお仕事です。
よく「答えはあなたの中にある」と言うアレですね。
その質問を、自分に向けて行うためには、目次を質問に仕立て上げるのが一番いいです。
10年以上前にフォトリーディングが流行ったとき、そのやり方のステップの一つに「質問を考えてから読む」と言うのがありました。
目次を読んでから、自分に向けて質問を作り、その答えを探すように読むんです。
それを昔経験したことがありましたから、目次を質問にすると言う読み方はそこからきているのだろうなと思います。
目次を質問にし、さらに答えて行くと、いつのまにか全体が俯瞰できるとともに、小さなことには拘らなくなります。
目次は本の柱ですから、ここを外さずに読むのがいいんですね。
全体を俯瞰して、小さく読み、また全体を俯瞰して、と言うことを繰り返しながら読むのは、その本、丸ごと自分のものにした気がしてなかなか読後の充実感があります。
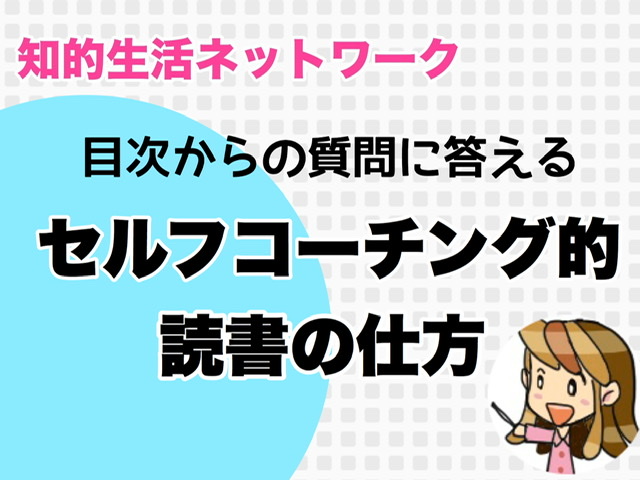
昨日の積み上げ
昨日できたほぼ唯一の積み上げ。
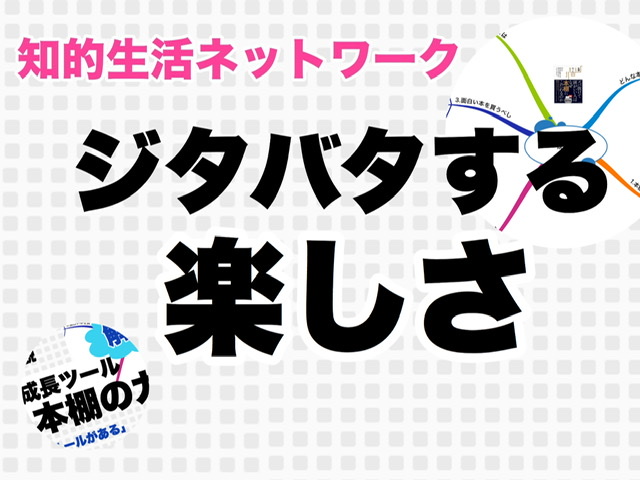
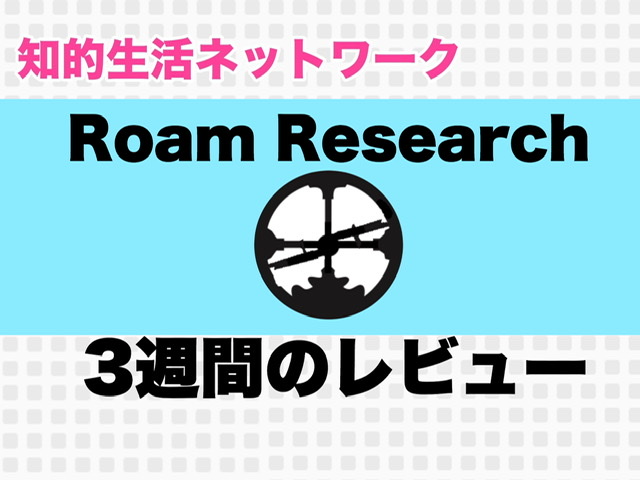
コメント