今は、本を出版するということは、イケハヤ氏の言葉を借りれば「民主化」されました。
以前は出版社かお金のある人しかできなかった出版ということが、個人でできるようになったからです。
そして、AIの登場により、今では1日1冊の出版も可能となりました。
目次
「出版の民主化」とは?~個人出版と自費出版の違い
まずは、「出版の民主化」ということについて抑えておきたいと思います。
そうであっても、個人で出版する方法は以前からありました。
そう、自費出版です。自分でお金を出して本を作るのです。
ところが、いわゆる出版とは大きな違いがあります。それは「販売網を持たない」ということです。
いくらお金をかけて立派な本を作っても、それを配ったり買ってもらったりする手段がほとんどないのです。
せいぜい自分のブログで売る、という程度しかできません。本屋においてもらうことなどほとんどできないのです。
その本を手に取ってくれるのは、自分に近いほんの身近の人だけ。
さらにそれらの本は、たとえ無料でもらっても読みたい本ではないから誰からも読んでもらえない。
つまり自費出版というのは、
🍏お金をかけて本を作り
🍏身近な人にしか配れないから在庫を抱え、
🍏ほとんど読んでもらえない
というものなわけです。
これに対して「個人出版」は、自分で販売網を持つプラットフォームで出版でき、沢山の人に喜んで読んでもらった上、収益まで入ってきます。
レビューで感謝されることもあります。
在庫ももつことはありません。
個人出版と自費出版とはこれほどちがうものです。
こうして、
🍏自分で書いた原稿を
🍏販売網を持つプラットフォームで出版し
🍏多くの人に手に取ってもらい、場合によっては感謝してもらい
🍏収益が入る
これが「出版の民主化」というものであると考えます。
特に収益化できるというところが大きな違いです。
自費出版はあくまで自分でお金を出すものです。「自己満足」と言えるかもしれません。
収益化までいけるから「民主化」なのです。
「出版の民主化」を可能にしたKindleダイレクトパブリッシング
2012年に、アマゾンがKindle出版の門戸を一般に開放しました。
このことで、個人がWordやGoogleドキュメントなどで書いた本をアマゾンの本棚におくことができるようになったのです。
こうして上記の「出版の民主化」への道が開かれました。
だれでも作家になることができるようになったのです。
個人出版と違い、アマゾンという巨大な本屋の一角にちゃんと自分の本が置かれていて、世界中の誰もが見ることができます。
これは、アマゾンが、その本棚に自分の本を置くことを許可してくれたということなのです。
つまりアマゾンが私のことを作家として認めてくれた、ということなのです。
「出版の民主化」とは、自称ではなく、名実ともに作家になることができるということをも意味します。
この私も、2016年に作家デビュー。2025年10月12日現在39冊の本を出版しています。
そして1日1冊の本を書ける時代へ
2012年からすでに13年たちました。これまで多くのKindle作家が生まれました。
しかし、そのうち10年間は、自分から個人出版を行おうとする人は身の回りにほとんどいませんでした。
それは大変だからです。
なんといっても、自分で15,000くらいの文字をタイプするというのは一般の人にとってはなかなか高いハードルなのです。
また、本にするアイデアもありません。
15,000字書くというよりも、むしろ「書くことがない」ということの方が、「本を書くことなんて考えられないよ」という気持ちの一番大きな理由かもしれません。
ところが、その両方を一気に打ち破るものがあらわれました。
AIの登場です。
書くことがないという壁を打ち破る
AIは、「書くことがない」の壁を打ち破りました。
AIに「本を書いてみたいんだけど・・・」と呟けば、「それは素敵、では一緒に考えてみましょう。」といって、いくつか質問をしてくれます。
それに答えているうちにいつの間にか「書くことがない」と思っていた私にいくつもの書くことが生まれてしますのです。
また、頭に何らかの小さな考えが浮かんだとき、それを膨らませて本にしてくれます。
「鬼二流道」という本があります。
これはウォーキングしているときに浮かんだ、「二流でいいじゃん」という言葉から生まれた本です。
AIが登場するまでは、おもしろい考えがうかんだ、と思ってメモに残すくらいが関の山です。
そのうち、ブログか何かで記事にすれば良いところで、そのまま埋もれていた可能性が高いでしょう。
ところが、ウォーキングの足をとめて「二流でいいじゃんという本を書きたいんだけど」となげかkたことで、25分後には本のラフ原稿ができてしまいました。
AIがまさか本になるとは思いもしないような、頭に浮かんだ小さな考えを膨らませてくれたのです。
AIはこういうことを可能にしました。「書くことがない」という壁を打ち破ってくれたのです。
たった5分で15,000字の原稿を書いてしまう
テーマが決まれば、すぐに章構成までつくってくれます。
「1章から順に書いて」というだけで、AIは章ごとに「次」とか「OK」とかいうだけで、「おわりに」まで書き上げます。
5分とかかりません。
「15,000字なんでとても書けないよ」」という私の限界突破がAIによって可能になりました。
こうして、AIの登場により、「書くことがない」ということと「そんなにたくさん書けない」ということがあっさりと打ち破られたので、Kindleダイレクト・パブリッシングでの個人出版は本当にだれにでも開かれてしまいました。
私は現在、ストアカで2時間半でゼロから執筆、出版まで行う講座をおこなっています。
この中で50分間、私のデモを見ていただきます。本当にゼロからテーマを作り、執筆をして出版までしてしまうところをみてもらうのです。
びっくりされますが、「たしかに自分にもできる」という実感をもってもらうことができます。
だから、その後の50分で本当に出版までできるようになるのです。
私はそのデモのために、講座があるたび、毎日のように出版していますので、「1日1冊の出版」というのは本当なのです。
「1日1冊出版するなんて、単なる『粗製乱造』だろ?」
「ちょっとまって!1日1冊って、もちろんAIだよね。それってすごく質の低い本を、ただ乱造してるだけじゃないの?」
そう思われるかもしれません。
ところが違います。
こちらの本を見てください。Kindle Unlimitedに加入している人は無料で読めますから。
これはAIを使って25分で書いた本です。
しかし、とてもよい評価を頂いています。
また、昨日も「これはかなりしっかり書かれていますね。」と褒めていただきました。
「粗製乱造」とは思えないのではないでしょうか?
AIで書かせたのに、なぜよい評価を頂いているのかと言うと、これは私の予想ですが、「企画をしっかりとしたから」ということだと思います。
現在出ているNanoBananaに関する本の情報、それからYouTubeにあるNanoBananaの動画、それらをできるだけ集めてNotebookLMに入れ、内容を分析させました。
そのうえで、ManusというAIエージェントで、どんあ切り口で書けばいいのか、構成はどうしたらいいのかを提案させたうえで、更に必要な情報は自発的に検索しながら執筆するということを自動的にさせました。
指示を出した後は、メルマガなど別の仕事をしていました。
こうして、素案となる原稿ができたのが25分後だったのです。
この企画をしっかりやったことが。AIで記事を書かせながらもよい評価をいただける本になった理由だと思っています。
つまり、AIを使って、その上でしっかりした本を書く要件は、「企画に時間をかける」ということだと言えますね。
とは言え、それも含めての25分だったのですが。
出した本を、責任を持って育てていくこと
企画をちゃんとやることで、内容のしっかりしたオリジナルな本はできます。
そしてあっという間に15,000字程度の本はつくれてしまします。
あとはCanvaで表紙を作り、出版手続きをすれば最短50分で本は出版できるのです。
この原稿を書いているのは2025年10月13日ですが、昨日も、一昨日も2日続けて本を出版しました。
一昨日は、公民館の研修で、昨日はストアカの講座で、それぞれ執筆から出版までのデモをお見せしたからです。
ところが、こうして出版した本は、最低限の情報の塊でしかありません。
とりあえずこれでも必要な情報は揃っているので、最低価格の99円をつけて販売しています。
しかし、このままでは読者に快適な読書経験を提供することはできません。
表紙は10分ほどでテンプレートを使って作ったものですので、そもそもクリックされるかどうかもわかりません。
原稿は、改行による空白など作っていないため、スマホで読んだ場合、画面全体を文字が覆ってしまっています。
強調や文字装飾、挿絵などのアイキャッチがないため、読むのに憑かれます。
なので、これから時間をかけてこういうことを一つ一つ改善していく必要があります。
まずは、行間を適切にあけたり、開業したりして読みやすくします。
それから、強調文字にしたり、色を変えたりなど、目を停めやすくします。
ときには挿絵を入れますし、NanoBanana本のように事例が必要な場合は、画像を入れていきます。
場合によっては、追記したり、文章を書き換えたりしていきます。
こちらの本は90%ほど書き換えて、ほぼ自分で書いたのと変わらない原稿になりました。
このように、一度出版した後は、そのままでなく、育てていくことが大事です。
「1日1冊出版」の考え方は、この「出版後の育成」を前提としているのです。
先に出版 あとから育てる
こう言うと、「それなら、しっかり完成させてから出版すればいいじゃないか」と思われるでしょう。
ところが、先に完璧にしてから出版しようとすると、それはただ出版を遅らせることにしかなりません。
私が一番よくわかっています。
なぜなら、私は2016年に初めての本を出版するまで、4年もかかったのですから。
2012年にAmazonがKindleダイレクト・パブリッシングを開放したとき、私にはすでに以原稿がありました。
2009年に本を出版することを志し、その墓3年かけて原稿を作っていたからです。
なので、私は、KDPが始まった時、大喜びで実際にその原稿を一度アップロードしました。
しかし出版ボタンを押すことができませんでした。
「これはだめだ。もっと構成から考えて読みやすくしないと・・・」
こう考えて、完成版を目指そうとしたため、その後何度も何度も構成から見直すことを繰り返しました。
そして、作家の倉下忠憲さんに背中をおしていただいて出版するまで4年もかかったのです。
2009年に志したときから数えると7年もかかったのです。
2012年にさっと出版しておき、その後修正するたびに「第2版」「第3版」と版を積み重ねていけば、私にはその4年分の経験が積み上がっていたのです。
本当に惜しいことをしました。
だから私は、メルマガやメンバーシップ、Podcastなどの情報発信において、」完全版を作郎とせず、まず出版してください」とお伝えしているのです。
こうして何人もの方がなんとか出版にこぎつけられています。
みな、最後の最後で足踏みをしたまま止まっていた人たちです。
なかには3年も出版ボタンの前で止まっている人もいました。
そんな人達も、今はみな出版し、作家になってもらっています。
あとは、さらなる出版を行いながら、それらを本を時間をかけてこれからも育てていくことです。
本をよりよく育てると何が起きるのか
こうして、まずは最低限の情報だけの本を出版し、最初の完成版をできるだけ早く再アップロードしてとりあえず完成版にした後は、第2版、第3版と積み重ねていきます。
古くなった情報を書き換えたり、新しい情報を書き加えたりしていくのです。
こうして本をじっくりと育てていくと何が起きるのか。
昨年、2024年の11月に私が初めてAIを使って本を書いた時、知り合いも1冊のAI生成本を出版しました。
その人は、その後半年の間、追記、修正を繰り返し、2版、3版と積み上げたそうです。
そうしていくうちに徐々にランキングが上がっていき、なんと6月頃のことですがベストセラーを取ってしまったのです。
本人は大喜びでした。
初めて書いた本が6ヶ月後にベストセラーになったのですから。
私も、毎日1冊は修正、追記を加えて、少しでもよくして再アップロードし、古い本が埋もれないようにしています。流石にベストセラーを取るまでは行きませんが、古い本も売れ続けています
2025年10月13日時点で39冊も出版しているので、毎日やっても、ある本が次にメンテナンスされるのに一ヶ月以上かかります。
その感覚は、今後本の冊数が増えるとともにどんどん広がるでしょう。
しかし、私の本はいつでも最新版だと言えるように、今後も「1日1冊」で出版した本は特にしっかりと育てていくつもりです。


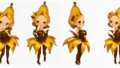
コメント