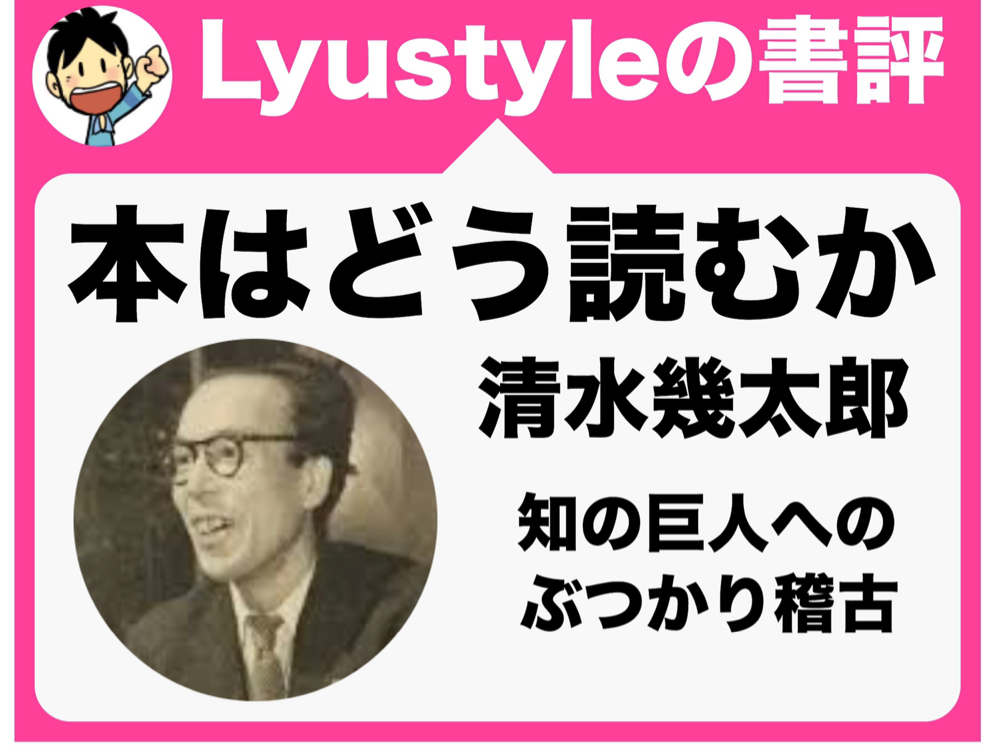
講談社現代新書で求めたこの本の奥付のところに「平成元年3月13日読了」と鉛筆で書かれていました。
昭和47年に第1刷が発売されたこの本を,私は平成元年に27刷で買いました。480円と書いてあります。
30年前,新書はワンコイン以下で買えたんですね。
平成元年3月13日といえば,私はようやく30代になろうとしていた頃。最初に赴任した学校での最後の卒業生を送り出す卒業式を1週間後に控えていた頃。
また,初めての異動を2週間後に控えていた頃。
やたらと忙しい毎日を送っていたころでした。
そんな不安定な時期に,よくこんな本を読み通したもんだと思います。
でも内容はそんなに入り組んだ,難解なものではありません。
清水幾太郎は,社会学者であり,評論家です。
一言でいうとどんな人か,ということをいろいろ調べましたら,Wikipediaのこの記述がとても分かりやすいと思いましたので紹介します。
「私は学生時代に、清水幾太郎のこの本(『社会学講義』)を何度くりかえし読んだかわからない。
実際1950年代において、清水ほど社会学の戦後世代に強い印象を与えた社会学者は他にいなかった。
この世代には、清水の『社会学講義』をむさぼり読んだ経験をもつものが多いのではないか。
それほど、この本が戦後日本の社会学の形成に果たした役割は大きかった。
富永健一「戦後日本の社会学」」
Wikipedia
そのような方の書かれた読書論はどのようなものか,と興味を持って30代になろうとする私はこの本を手に取ったのでした。
はしがきの中で,
「どういう本を読んだらよいか。
どういう方法で読んだらよいか。
読んで得た内容を忘れないためには,どうすればよいのか。
蔵書の整理には,どういう方法があるか。
外国書になれるには,どうしたらよいか。
~私の経験を回顧しながら,一つ一つ,右の諸問題に応えようとしたものである」
と書かれています。
見るだに,飛びつきたくなるような内容です。
当時,私はこれを通読した記憶はまったくないのですが,30年ぶりに読んでみて,時代の制約があったとはいえ,今でも十分に通用する内容の宝庫であり,改めて興味深く読み通すことができました。
目次
「面白さも成長する」
子どもの頃,お小遣いをためては買いそろえ,読みふけってきた立川文庫に,ある日突然別れを告げるシーンがあります。
全巻箱に入れて,友達にやってしまうという,ある面ショッキングなシーンです。
あれほど面白いと思っていた立川文庫が,ある日まったくおもしろくなくなった。
大事な大事な本を友達にきれいさっぱりやってしまうというこの出来事は,知的に成長し,これまでの自分に別れを告げる儀式であったわけです。
なんという印象的な,知的成長の姿でしょうか。
このような経験をした人は、当時少なからずいたのではないかと思います。今の子どもがあんなに夢中になって読んだ「しまじろう」に飽き、「ドラえもん」に飽き・・・・。
そこに見られる成長が、当時はもっと高いレベルで行われていたような気がします。
「書物の内容が,自分を素通りしてノートにいってしまった」
ここでは,ノートのとり方についての話が述べられています。
何かの勉強を始めるとき,新しいノートを求めて,「さあ,この本のエキスを,神髄を,エッセンスをあますところなくこのノートに書くのだ」と息まいてノートを取り始め,そのうち失速して断念したというようなことはだれにでもあることでしょう。
幾太郎青年も同じ経験をするのですが,さすがに,心に鞭打って,本を一冊ノートにします。そしてその後,内容をおぼえていないことにショックを受けるのです。
それを「原本の内容は,私の心を通過して,ノートへ移ってしまった」と表現します。
清水幾太郎は,このようなノートのとり方を「客観主義」といいます。
人がそのような時期を経るのは致し方のないものです。また,それが必要なシチュエーションもあるとした上で,結局,理解したこと,納得したことを自分の文章で表現して初めて心の底に理解が生まれるといいます。
「読んだことはアウトプットして初めて理解できる」とさまざまなところで言われたり書かれたりしています。
「読書は「アウトプットが99%」にしても然り。
Lyustyleの読書22 で紹介した「つながる読書術」, Lyustyleの読書7で紹介した「齋藤孝の知の整理力」 も然り。
清水幾太郎も,1972年の時点で,ご自分の経験から同じことを言っていました。
「それでも私は古典がおもしろいと思えるようになりたい」
清水幾太郎は,
「古典や名著が面白く感じられないのは,自分が悪いのではないか,そう感じるのが人情であろう。
しかし,~自分の心の歯車と噛み合わぬ本は投げ出した方がよい。敗北感や劣等感は無用である」
と書きます。
まるで僕に言われているかのようです。
古典なんて,たまたま時代を超えて生き延びてきたラッキーなものなのであって,そもそもその古典が生まれた時代と今とでは,感じ方,考え方なども大きく変化しているはずなのだから,
当時有益であったとしても今なお有益であることの方がすくない,ことさらありがたがって読もうと思うのは時間がもったいない,というのです。
私はそこに折り目を入れてこんなことを書いていした。
「でも私は,それがおもしろいと思えるようになりたいのだ」
いくら清水氏がそのように言われても,「私はそうは思いませーん」と宣言しています。
これまで面白くてたまらなかった立川文庫がある日突然おもしろくなくなるように,
これまで面白くもなんともなかった「孤独な散歩者の夢想」が,ある日突然めちゃくちゃ面白くなったとしたら,これは,もう私の知的成長以外の何物でもない。
そうなったら,これはものすごい得です。
だから,私は今,面白くない本を,それでもたんたんと読み重ねるという読書法をとっています。
清水氏に対するぶつかりげいこです。
「本はちびちび読むな」
また,こうも言われます。
「多くの書物は,一度は一気に読まねばいけない。
一気に読むと,多少の疑問は残るであろうが,その反面,あの全体的構造が見えてくる。
細部は分からなくても,構造の輪郭がわかってくる。
急所が判ってくるといってもよい。
急所は,ちびちび読んでいたのでは,絶対にわかるものではない。」
これに対して,私はまた折り目を入れてコメントを書いています。
「とはいってもなあ・・・」
そうです。
わたしは「チリツモ読書」によって,日々読書の時間を捻出している人間です。
一気に読む時間などありません。
そんな忙しい人には,毎日少しでも読書を続けるというスタイルが必要なのです。
いかに清水氏が「ちびちび読むな」と言っても,ここは譲れません。
ちびちびでも読まないと,本を読むことができないのですから。
これも,知の巨人に,ぶつかりげいこ。
ただし,ここには,ライプニッツの,本居宣長のあの勉強法が書かれています。
そう,まずはさっと読み,それを再読しながら理解していくという方法です。
一気に読む,ということを,一度に読むという意味ではなく,分からない箇所があってもこだわらずに通読するという意味だと理解しています。
これは,「最後まで読むこと」と一項起こして書かれています。わからない箇所があっても,あまり考え込む必要はなく,先へ進めと。
「洋書の場合は,絶対に途中でやめてはいけない。内容がわからなくてもよいから,必ず最後のページまで読み通すことである」とも書かれています。
知の巨人は,古今東西を問わず,同じことを言うものですね。
この点は,拍手喝さい。僕にはこの勉強法しかとれないですし。
こちらの記事も読まれています
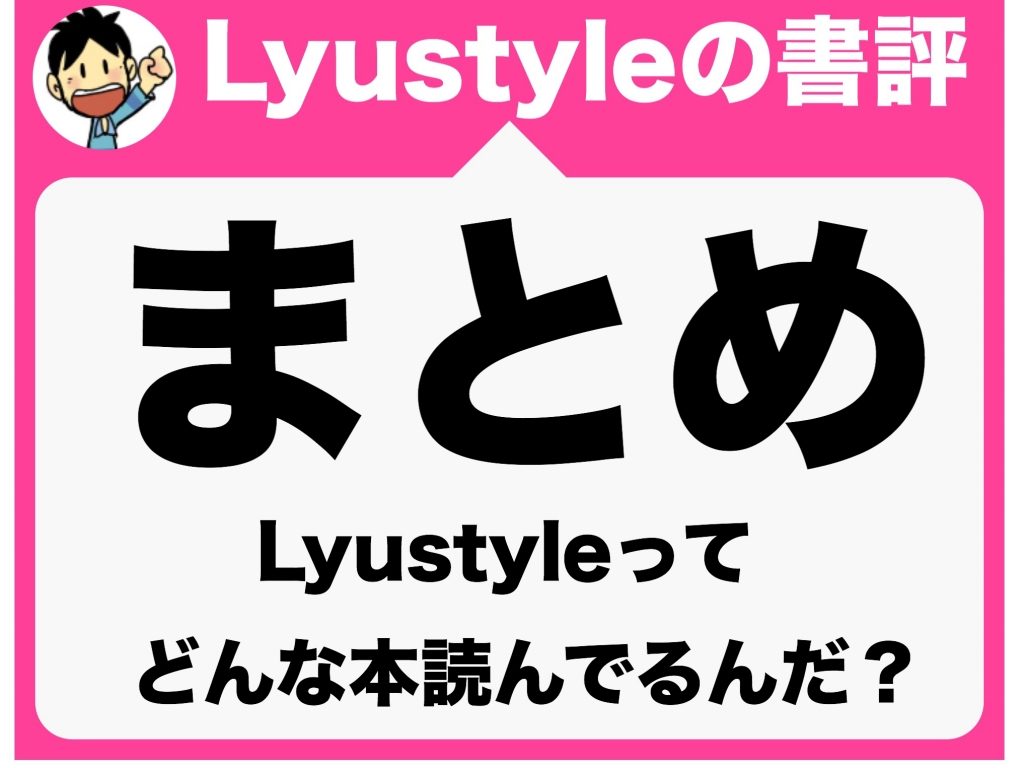
私のメルマガで配信している書評を記事にしてまとめています
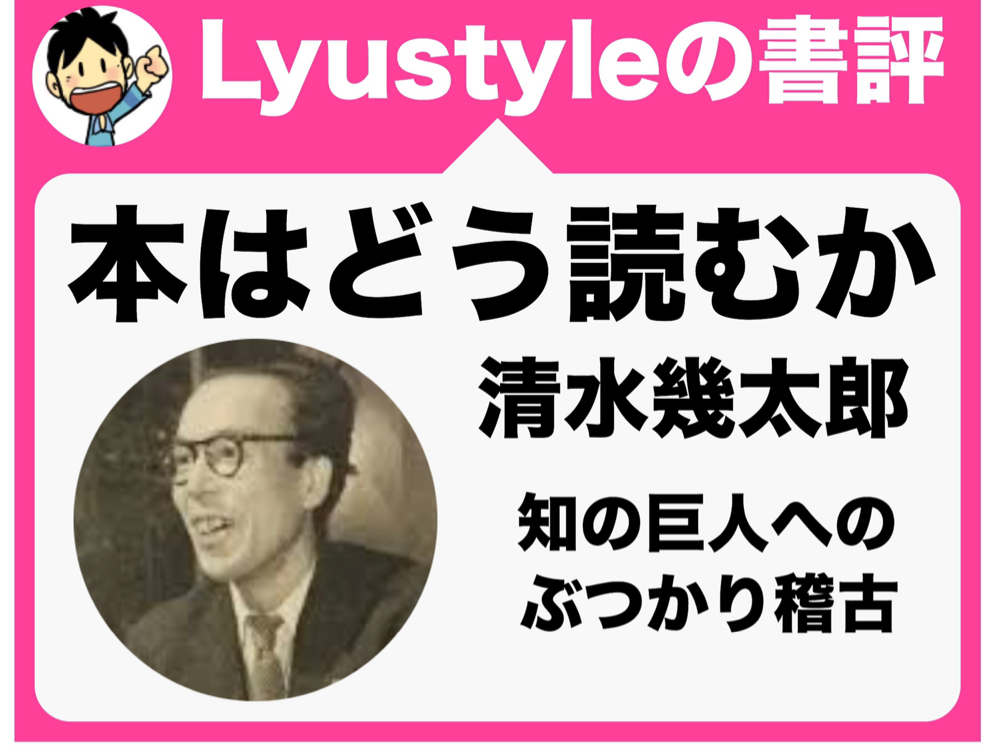
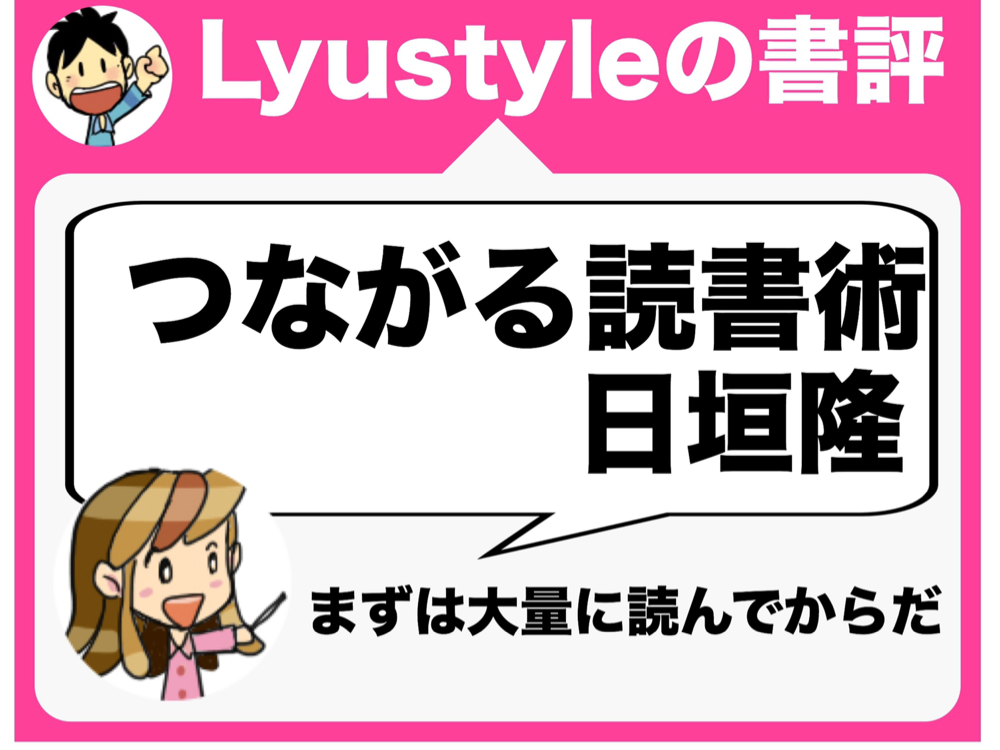
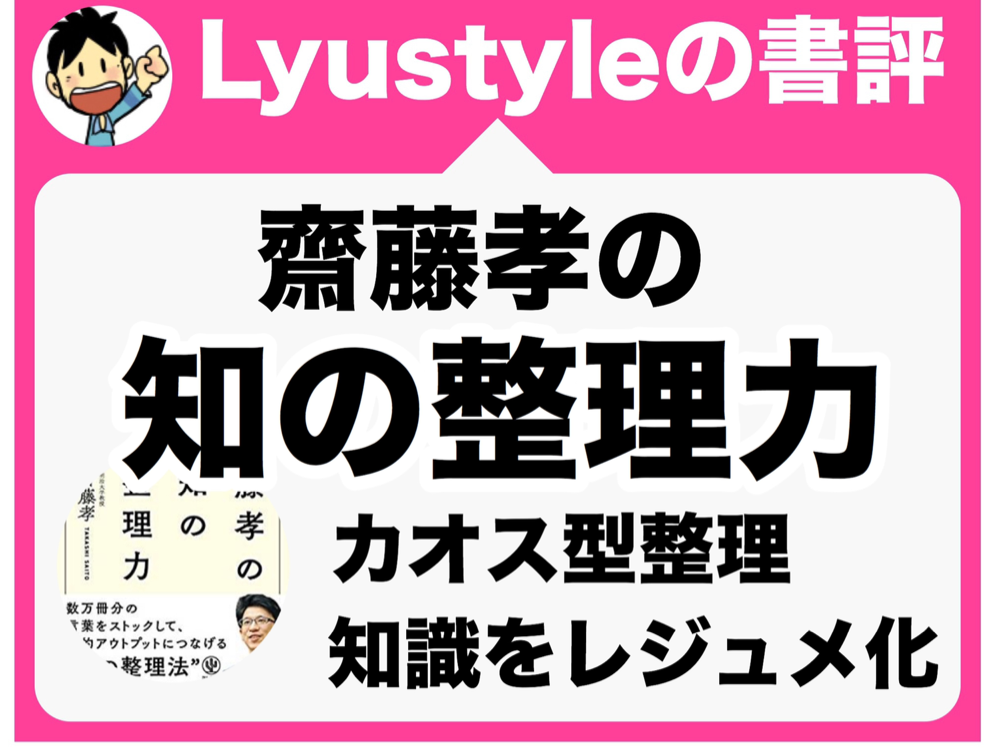
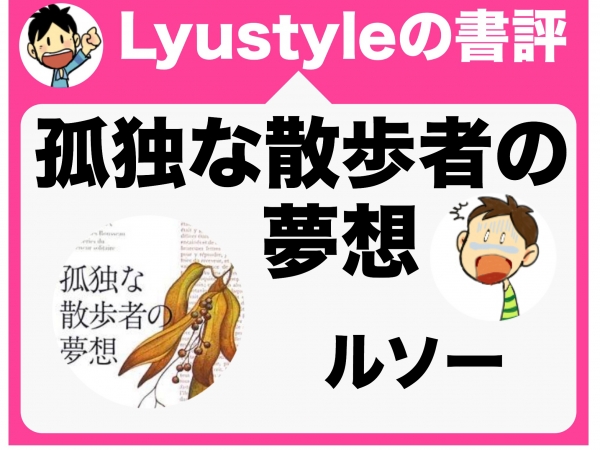
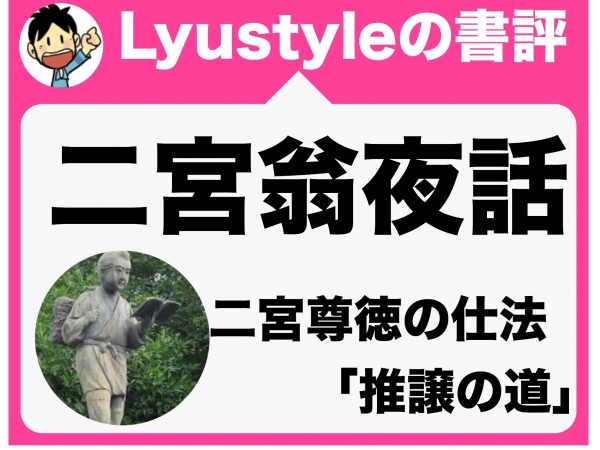

コメント
[…] 🍏本はどう読むか […]