夜に出ている「日記」というジャンルには2種類あります。「読まれてしまった日記」と「読ませるために書いた日記」です。
もともと本になるなんて思いもしなかったプライベートを赤裸々に書いた日記。これは読まれたくない日記です。
それに対して,後々本として夜に出回るだろうということを意識して書いたにきい。これは読ませる日記です。
この違いについて,その代表的な日記から考えてみます
※2022-2-12 更新しました
目次
読まれたくない日記
元禄御畳奉行の日記という本があります。
元禄時代に書かれた「畳奉行」という役職についていた武士の日記です。

芝居が好きだったり、大酒飲みでその度に後悔するものであったり。
芝居好きがいつの間にか芝居論評家となる。
ある時は安心し、ある時は発奮する。
好きなことをただ書き続けることができるということは素晴らしいです。
日記は、その人の人生と自分とを重ね合わせて見ることができる。
これ,横山光輝によるマンガも出てるらしいですね。
後世の私達は,当時の人の生活ぶりがわかる日記をとても興味を持って読みます。
「読み物」として読みます。
しかし,これを書いた本人は,後世,自分のプライベートの記録が読み物として読まれるということを考えたことがあったのでしょうか。
もちろん,ないと思います。
だから,赤裸々な感情や出来事がそのまま伝わっていておもしろいし,歴史の第一級資料となるわけです。
しかし,ところどころ,人にはわからない暗号のような書き方をしているところがあるほどですから,読まれてしまう,ということは意識していたことも間違いないですね。
この「読まれてしまう」とは,まさか本になって何百年後の人に読まれることを想定していたのではなく,あくまで身内,せいぜい数代後くらいまでの身内を想像していたのではないかと思いますがいかがでしょうか。
読まれることと,読まれてしまうことをは意識上の違いがあります。
読まれてしまう,という意識は,「隠す」という書き方になります。
あくまでもプライベートのことを書くのですが,読まれてもばれない,という書き方をするわけですね。
なら,書かなきゃいいのに,と思いますが,それを書くのがまた日記です。
バレるかもしれないとおそれつつ,それでもやはりばれないようにした上で書きたいのです。
あくまでプライベートを書くものです。
読ませる日記
これに対して,「読まれる」ということを前提とした日記は,それなりにあります。
永井荷風の「断腸亭日乗」などは,その例だと言われています。
日記の体をしつつ,読みものを意識して書いているわけです。
これは日記と言えるのでしょうか。
それを読む私達は,昭和の初期の東京の風情や人の考え方にとても興味を持って読みます。
うそがかいてあるわけではないので,ある程度底に書かれていることの信憑性を信じて読んでいます。
しかし,行動の仕方や考え方に若干の誇張があるのは事実ですので,その点,差し引いて読まないといけないということもわかって読んでいます。
資料という読み方ではなく,あくまで「読み物」として,永井荷風が意図した読み方で読んでいるわけです。
こう考えると,「断腸亭日乗」という日記は,読みものとして誇張して書いたものではあるけど,プライベートなことを書き記した日記であることには間違いないでしょう。
あなたが書いている日記は「読まれたくない日記」か「読ませる日記」か
では,あなたが書いているその日記は,どちらですか。
おそらく構成に読まれるようになるだろうから・・と,本を書くつもりで書いている人はそうはいないでしょう。
自分以外に読む人を想定していない「読まれたくない日記」のはずです。
しかし,心のどこかで,自分がこの世から旅立ってしまった後,必ず家族から読まれるよなぁ,ということはうすうす感じているはずです。
なので,書きたいことがあっても「これは書いたらまずい。棺桶の仲間で持っていこう」と思って書いていないものもあるのではないでしょうか。
これは「読まれる」ことを想定して,書いていいものと改定はいけないものとを選別している点で,「読まれる日記」であると言えます。
こう考えていくと,日記というものは,どう書いても「読まれたくないけど読まれる」というものであると言えますね。
つまり「必ずいつかは読まれる。それは今日ではない。でも後日確実に起きる」ということを確信し,覚悟して書いているものだと言えます。
つまり日記というものは「覚悟」を促すものだということですね。
「元禄御畳奉行日記」のように本として流通する第一級資料にならないとも限りませんから。
更新履歴
2017年5月12日 公開
2020年6月22日 追記
2020年9月27日 タイトル更新
2022年2月日 追記しました

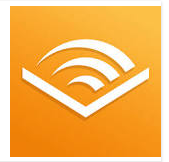

コメント